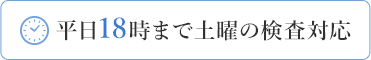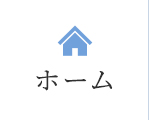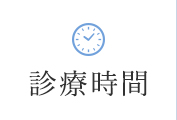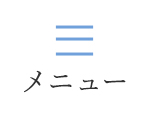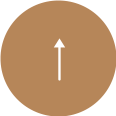過敏性腸症候群とは
 過敏性腸症候群は、腹痛、下痢や便秘、腹部膨満感などの症状を慢性的に起こす疾患で、大腸カメラ検査で大腸粘膜を観察しても炎症や潰瘍などの病変が発見されないことが大きな特徴です。
過敏性腸症候群は、腹痛、下痢や便秘、腹部膨満感などの症状を慢性的に起こす疾患で、大腸カメラ検査で大腸粘膜を観察しても炎症や潰瘍などの病変が発見されないことが大きな特徴です。
明確な原因はまだわかっていませんが、ストレスが発症に関与していることは多くの研究で報告されています。ストレスを感じると、脳下垂体からストレスホルモンが分泌され、その刺激により腸の機能が乱れ過敏性腸症候群の症状を起こしていると考えられています。また、それを繰り返すことで軽い刺激にも強く反応する知覚過敏を起こし、ちょっとした刺激をストレスと感じてさらに症状を起こしやすくなる負のスパイラルに陥って症状が進行すると指摘されています。
日本人全体の約10~15%の方が過敏性腸症候群という指摘もされており、消化器疾患の中でも発症頻度の高い疾患です。「1日に何度も腹痛がある」、「電車に乗るとお腹が痛くなる」といったような症状は、仕事や学業などの日常生活に大きな支障を及ぼしてしまいます。体質や気持ちの問題と誤解されやすいのですが、症状や状態、ライフスタイルなどに合わせた適切な治療を受けることが大切です。
過敏性腸症候群の原因
根本的な原因についてはまだはっきりと解明されていませんが、発症に関与する要因はある程度わかってきています。下記は、様々な研究で報告されている発症要因です。
ストレス
消化管は自律神経でコントロールされているので、ストレスによって自律神経のバランスが崩れると、下痢や便秘、腹痛、膨満感などの症状につながります。
大腸の蠕動運動
自律神経のバランスが崩れると、消化管の内容物を先に送る蠕動運動が亢進や低下を起こし、それによって症状を起こすことがあります。
大腸の知覚過敏
腸内フローラの変化、ストレスなどでホルモン分泌のバランスが崩れて知覚過敏を起こすことがあります。知覚過敏により、わずかな刺激に対して過剰な反応を起こしてしまい症状を起こします。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群の症状は主に下痢型・便秘型に分けられ、さらに下痢と便秘を繰り返す交代型もあります。また、腹部膨満感を強く感じるタイプも存在します。
緊張や不安などによって症状が誘発されるケースがあり、睡眠中に症状を起こすことが少ないのも特徴です。
下痢型
急激に激しい腹痛を起こし、トイレに駆け込むと水のような下痢になるというのが典型的な下痢型の症状です。排便後は症状が軽減しますが、こうした症状を1日に何度も起こすことがあります。男性に多く、通勤や通学の際の電車内や、会議・テストなどのストレスがかかるタイミングで症状が起こりやすい傾向があり、悪化すると外出がままならなくなるケースもあります。
便秘型
慢性の便秘に腹痛や腹部の不快感、排便後の残便感などが伴います。女性に発症が多い傾向があります。。
交代型
便秘と下痢を繰り返し、腹痛や腹部の不快感が伴います。
その他
腹部膨満感、お腹にガスがたまる、おならが出やすい、腹鳴など、排便とはあまり関係のない症状を起こします。便表面にヒビが入るような硬めの便や、ちぎれるような軟便がみられることがあります。
過敏性腸症候群の検査
 自覚症状や排便の状態、生活習慣やストレスの有無などについての問診を行います。血液検査や大腸カメラ検査を行い、大腸に炎症やがんがないことを確認します。過敏性腸症候群の主な症状である腹痛、下痢や便秘は他の多くの大腸疾患でも現れる症状ですので、大腸カメラ検査で大腸の状態を確かめ、病変が発見されない場合に過敏性腸症候群と確定診断されます。辛い症状のある疾患ですから、大腸カメラ検査を行って早めに診断することで、症状改善のために有効な治療をより早くスタートできます。
自覚症状や排便の状態、生活習慣やストレスの有無などについての問診を行います。血液検査や大腸カメラ検査を行い、大腸に炎症やがんがないことを確認します。過敏性腸症候群の主な症状である腹痛、下痢や便秘は他の多くの大腸疾患でも現れる症状ですので、大腸カメラ検査で大腸の状態を確かめ、病変が発見されない場合に過敏性腸症候群と確定診断されます。辛い症状のある疾患ですから、大腸カメラ検査を行って早めに診断することで、症状改善のために有効な治療をより早くスタートできます。
過敏性腸症候群の治療
個々の症状に合う薬を服用することによって症状を緩和させ、食生活を含む生活習慣の改善に取り組むことで、症状の解消や再発防止につなげています。
薬物療法
腹痛や下痢・便秘の症状を緩和する薬を中心に、整腸剤など消化管の状態を整える薬を併用します。蠕動運動を改善する薬、腹痛を抑える薬、便の水分バランスを整える薬、腸内フローラのバランスを改善するプロバイオティクスなど、様々な薬の処方が可能です。こうした治療薬には作用機序が異なるものも多く、同じ薬でも効果の出方には個人差がありますので、症状の内容だけでなく、現れやすいタイミング、お困りの点、ライフスタイルなども丁寧に伺った上で処方、調整しています。
また、強いストレスが発症に関与している場合には、抗うつ薬や抗アレルギー薬によって高い改善効果を得られることもあります。
なお、薬物療法の薬には即効性のあるものもありますが、服薬を2ヶ月程度続けて効果が現れるものもあります。焦らず気長に構えて治療に取り組んでいきましょう。
生活習慣の見直し
睡眠や休息を十分にとり、規則正しい生活を心がけ、適度な運動を習慣付けましょう。ストレスを解消するために、熱中できるスポーツや趣味のための時間を積極的に作ることも有効です。入浴、マッサージ、ストレッチなども気分を変えるためのきっかけにできます。
食生活の改善
- 食べ過ぎ、飲み過ぎを控える
- 栄養バランスに配慮した食事をとる
- 1日3食を規則正しくとる
- 就寝の3時間前までに夕食を済ませる
- 飲酒を控える
- 刺激が強い香辛料、カフェイン、炭酸飲料を控える
- 脂質をとり過ぎないようにする
こうした生活習慣の改善を続けることで、症状緩和だけでなく、再発予防にも役立ちます。
生活習慣改善全体に言えることですが、無理せずできることから行っていくことが重要です。厳しい内容では続けるのが難しく、ストレスとなり症状を悪化させる可能性もありますので、頑張り過ぎは禁物です。