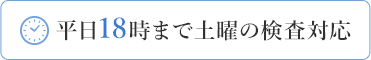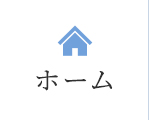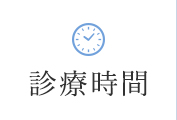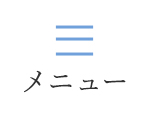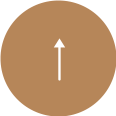血便・下血・便潜血
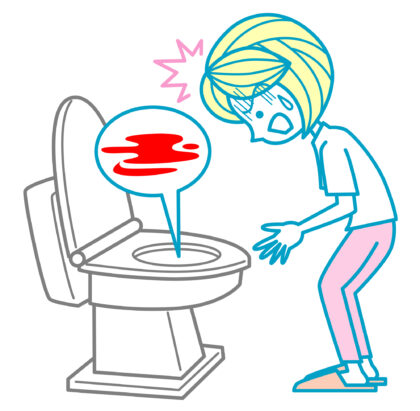 消化管(口から肛門まで)内で起こる出血を消化管出血と言い、血便や下血の原因となります。血便とは便に血液が混入した状態です。血便は、肛門や大腸などの下部消化管からの出血が想定されます。全体が赤っぽく、血液と粘液が表面に付着したタイプ、血液のみが出るタイプ、排便後ペーパーに血が付くタイプなどがあります。
消化管(口から肛門まで)内で起こる出血を消化管出血と言い、血便や下血の原因となります。血便とは便に血液が混入した状態です。血便は、肛門や大腸などの下部消化管からの出血が想定されます。全体が赤っぽく、血液と粘液が表面に付着したタイプ、血液のみが出るタイプ、排便後ペーパーに血が付くタイプなどがあります。
一方で、下血は胃や十二指腸などの上部消化管からの出血で、黒いタール状の便が排泄されます。血液が便として排泄される過程で消化酵素や胃酸によって酸化されるため黒色の便となります。
目視できないくらい少量の血液が混ざっているかどうかは、便潜血検査で判断します。
健康診断などで実施する便潜血検査は、1日または2日にわたり便の一部を採取して特殊な検査を行うことにより、非侵襲的に少量の血液を検出することができるため、大腸がんのスクリーニング検査として行われます。便潜血陽性とは、消化管のどこかに病変がある可能性があることを意味します。必ずしも大腸がんなど重篤な疾患によるものではないこともありますが、原因を調べるために速やかに大腸カメラ検査による精密検査を受けましょう。
血便と消化器疾患
大腸ポリープ
小さいときは無症状ですが、大きくなると出血したり便に粘液が付着したりすることがあります
大腸がん
初期の段階では無症状のことが多いですが、大きくなると便に血液や粘液がまじることがあります。他にも、便が細くなる(便柱の狭小化)、便秘や下痢を繰り返す、腹痛、残便感、倦怠感、食欲不振などといった多彩な症状がみられます。
虚血性腸炎
大腸の血流が急に悪くなることにより、腸の粘膜が傷つき血便と腹痛をきたす疾患です。
症状は一過性のことがほとんどですが、他の疾患と区別がつきにくいため自己判断せずに、必ず医師の診察を受けるようにしましょう。
潰瘍性大腸炎・クローン病
どちらも難病に指定されている疾患です。潰瘍性大腸炎は、直腸を中心に炎症を起こし、血便の他に、粘液便、腹痛、発熱といった症状を伴います。一方、クローン病は主に小腸や大腸で炎症を引き起こす慢性疾患で、下痢や腹痛といった症状を繰り返します。
細菌性腸炎
カンピロバクターやサルモネラ、病原性大腸菌などの細菌が原因で起こる急性の腸炎です。
食べ物や水を介して感染します。血便の他にも腹痛や発熱、下痢、嘔吐といった症状を伴います。
大腸憩室出血
大腸憩室は、腸管内の圧力が高まることによって、腸壁の一部が袋状に外側に突出する疾患です。憩室があっても大部分は無症状ですが、まれに出血や炎症を起こすことがあります。
憩室からの出血時は、出血のみで腹痛を伴わないことも多いです。
痔
切れ痔(裂肛)やいぼ痔(痔核)によるもので、排便時にトイレットペーパーに少量付着する程度のものから、便器が真っ赤になるぐらい出血したりすることがあります。肛門の痛みや鮮血(あざやかな出血)を伴うことが多いのが特徴です。
便潜血検査で陽性となった場合
 便潜血検査で陽性となった場合、詳しい検査を行うと、大腸がんが見つかる確率は数%と低いですが、がん化リスクがある大腸ポリープが見つかる確率は30~40%です。見つかった大腸ポリープは、検査中に日帰り切除も可能です。ポリープを取り除くことで、大腸がんの発症を防ぐことに繋がるため、便潜血検査陽性となった方は、なるべく早めに大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。
便潜血検査で陽性となった場合、詳しい検査を行うと、大腸がんが見つかる確率は数%と低いですが、がん化リスクがある大腸ポリープが見つかる確率は30~40%です。見つかった大腸ポリープは、検査中に日帰り切除も可能です。ポリープを取り除くことで、大腸がんの発症を防ぐことに繋がるため、便潜血検査陽性となった方は、なるべく早めに大腸カメラ検査を受けることをお勧めします。
血便・下血がみられたら
 血便や下血の症状があるときは、重大な疾患が隠れていることがあるので、自己判断をせずに一度医療機関を受診し、きちんとした診察を受けることを推奨します。
血便や下血の症状があるときは、重大な疾患が隠れていることがあるので、自己判断をせずに一度医療機関を受診し、きちんとした診察を受けることを推奨します。
大腸がんを防ぐためには
血便の症状が現れる病気は様々なものがありますが、発症率やがんによる死亡者数が増加傾向にある大腸がんは早期発見することが大切です。早期発見によって生活の質を落とすことなく完治が期待でき、がん化リスクがある大腸ポリープを取り除くことで発症防止に繋がります。一番の予防策は、定期的な大腸カメラ検査の受診です。発症しやすくなる40代を迎えたら、定期的に大腸カメラ検査を受けることを推奨いたします。