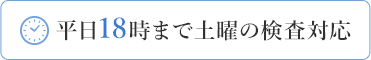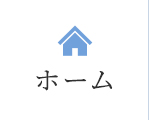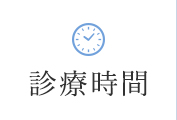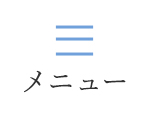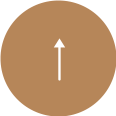このような症状はありませんか?
- 食欲が2週間以上もわかない
- 食事に対して面倒くささがある
- 食欲がなくて、体重が減った
- 胃痛や腹痛のせいで食べたくない
- 食べても味がしない、味覚がおかしい
食欲不振とは

食欲不振とは、「食欲がわかない」状態です。「空腹を感じない」、「食事が偏る」と自覚されることもあります。脳と消化器系には深い関係があり、脳からの「お腹が空いた」という指令が何かしらの原因で発せられなくなると、食欲不振になる場合があります。
食欲不振が長引くと、栄養状態の悪化や体調不良、免疫力の低下をきたします。食欲不振は、疲労やストレスなどによる一過性のものもあれば、何かしらの病気が隠れていることがありますので、原因を特定することが大切です。
食欲不振の原因
食欲不振の主な原因として、疲労やストレス、生理的要因、消化器疾患、消化器以外の疾患があげられます。
疲労やストレス
過労などの肉体的ストレスや精神的ストレスによって自律神経のバランスが乱れ、副交感神経の働きが弱まると食欲不振になります。
生活習慣の乱れ
不規則な時間の食事、お酒の飲み過ぎ、運動不足、睡眠不足などが原因で食欲不振になる場合があります。
生理的要因
月経や妊娠などで生理的に食欲が低下することがあります。
食欲不振を起こす主な消化器疾患
- 逆流性食道炎
- 食道がん
- 慢性胃炎(萎縮性胃炎)
- 機能性ディスペプシア
- 胃・十二指腸潰瘍
- 胃がん
- 膵がん
- 過敏性腸症候群
- 大腸がん
消化器以外の疾患
インフルエンザ、風邪、気管支炎、肺炎などの感染症
脳疾患、心疾患、頭痛、肝臓疾患、腎臓疾患、電解質異常などにより食欲不振が生じることがあります。
甲状腺機能低下症(橋本病)
甲状腺の機能が落ちると、甲状腺ホルモンの分泌量が少なくなり、倦怠感、疲労感、全体的な活力の低下、食欲不振が起こります。
うつ病
うつ病によって食べ物への関心が失われ、食欲が低下して体重減少に繋がる場合があります。症状を解消するためには専門医による治療が必要です。
食欲不振・体重減少の検査
問診で食欲不振が現れた時期や頻度、付随症状、服用中の薬や基礎疾患、ライフスタイルなどをお聞きします。問診の情報をもとに必要な検査を行います。
血液検査
現在の状態の評価やスクリーニング検査、各ホルモン検査
超音波検査・CT検査
器質的な病変がないか調べます。
食欲不振・体重減少の治療
原因が見つかった場合は、その疾患の治療を優先的に行います。
生活習慣の見直しや運動療法、ストレス発散などの指導・アドバイスを行いますので、一度ご相談ください。