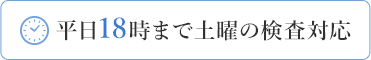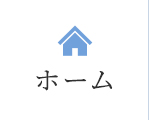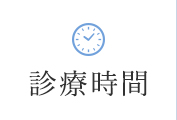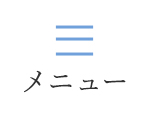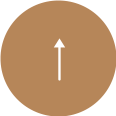高血圧症
高血圧とは

高血圧は、血圧が高い状態が続くことをいい、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上と定義されています。日本では約4300万人が高血圧と推定され、そのうち約3100万人が血圧管理が不十分といわれています。高血圧の状態が長く続くと、血管に負担がかかって動脈硬化が進み、脳卒中や心血管疾患、腎臓病などがおこりやすくなります。
高血圧の原因
高血圧の約9割は「本態性高血圧」で、原因が明らかでなく、食塩の取り過ぎ、喫煙、肥満、運動不足、多量の飲酒などの環境要因や、遺伝的要因などが関係しているといわれます。残りの1割は、ホルモンの異常や腎臓や心臓の病気など、原因がはっきりしている高血圧です(二次性高血圧)。
高血圧そのものは通常症状がなく、健康診断などを通じて早期に発見し、適切に対応することが大切です。
高血圧の治療
診察室での血圧、家庭で測定した血圧をもとに、治療が必要かどうか判断します。
治療の目的は、脳卒中や心血管疾患の発症や進行を防ぐとともに、生活の質を保った日常生活を送れるようにすることです。塩分摂取量を控えること、適正な体重を保つことは血圧を下げるのに効果的です。内服治療や生活習慣の改善によって適正な血圧を維持することが治療目標になります。ライフスタイルなども考慮したうえで、できるだけストレスのない、日々続けられる治療を行います。
脂質異常症
脂質異常症とは
脂質異常症とは、LDLコレステロール(悪玉)や中性脂肪が必要以上に増えたり、HDLコレステロール(善玉)が減っている状態です。脂質が過剰な状態が持続すると、動脈硬化を招き、狭心症・心筋梗塞などの心疾患、脳梗塞や脳出血、慢性腎臓病の原因となります。
脂質異常症の治療
脂質異常症の治療の3本柱は、食事療法・運動療法・薬物療法です。
食事療法は、動物性脂肪を含む食品を減らして植物性脂肪を含む食品を増やす、野菜やきのこ類などの食物繊維を多く含む食品を積極的に撮る、中性脂肪が高い方は糖質の多い食品やお酒を控える、などを心がけます。
運動療法は、ウォーキングや軽いジョギングなどがお勧めです。こうした有酸素運動を続けることで、中性脂肪を減らし、HDLコレステロールを増やすことが知られています。
内服治療については、年齢・性別・喫煙の有無・心疾患の既往症などの因子だけでなく、患者さまの治療に対する考え方を大切にし、専門的な立場からその方に最良の治療を行います。
糖尿病
糖尿病とは

糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンの作用が不十分なために血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が正常範囲を超えて高くなる病気です。糖尿病は大きく「1型」と「2型」に分けられます。日本人では2型糖尿病が圧倒的に多く、その発症にはインスリンの分泌不足といった要因に加え、過食、肥満、運動不足、ストレスなどの生活習慣が関係しているといわれています。
糖尿病は初期症状が乏しく、目立った症状が現れることなく進行することが多い病気です。口喝、多飲、多尿、体重減少といった自覚症状が現れたころには、ある程度進行してしまっていることもあります。さらに、病気が進むと三大合併症と呼ばれる糖尿病網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病神経障害を発症して、末期には失明したり、透析治療が必要になったりすることもあります。また、心筋梗塞や脳梗塞など、命に関わる病気を引き起こす可能性も高まります。そのため、早いうちから、血糖値をコントロールすることが大切です。
糖尿病の診断は、症状の有無、ヘモグロビンA1cの値、血糖値を総合的にみて診断していきます。
糖尿病の治療・予防
食事療法
糖尿病の治療において、糖(ブドウ糖)の摂取量を適切にコントロールすることが重要です。ただし、糖の摂取量を減らすだけでなく、バランスの取れた食事を適量摂取することも重要です。
運動療法
適度な運動は、糖尿病だけでなく他の生活習慣病の予防や管理にも重要です。運動によって糖の消費が増えるため、血糖値を下げる効果が期待できます。また、筋力をつけることで筋肉が糖をより効率的に取り込むことができ、同時に脂肪を燃焼しやすくします。
薬物療法
糖尿病の治療には、経口薬や注射薬など様々な種類の薬が使用されます。これらの薬は、インスリンの分泌を促進したり、接種した糖の分解や吸収を遅らせたり、排泄を促進することによって血糖値のコントロールをサポートします。
このような症状のある方はご相談ください
- 健診などで「血糖値の異常」を指摘された
- よく食べているのに痩せる
- ひどくのどが渇く
- 尿の回数や量が多い
- 手足がしびれる
- 足がむくむ
- やけどやけがの痛みを感じない
- 視力が落ちてきた など
高尿酸血症・痛風
高尿酸血症とは
「高尿酸血症」とは、血液中の「尿酸」の濃度を示す尿酸値が7.0mg/dLを超えている状態のことです。痛風だけでなく、慢性腎臓病、尿路結石の原因となります。脂質異常症、高血圧や糖尿病との合併が多くみられます。
痛風発作
尿酸が高い状態が続き、尿酸の結晶が関節にたまり炎症がおきるのが「痛風」です。主に足の親指の関節が赤く腫れ、激しい痛みを起こします。
痛風発作の痛みがある間は、炎症を抑えて症状を緩和する治療を行います。症状が落ち着いたら血液検査で尿酸値を調べ、状態や既往症などに合わせた治療を行います。
高尿酸血症の治療
食べ過ぎや、プリン体がたくさん含まれる食品や脂肪のとり過ぎ、運動不足は尿酸値を高めるため、生活習慣の見直しが大切です。特に、アルコールの過剰摂取は控えるようにしましょう。女性では、血清尿酸値が7.0mg/dlを超えていなくても注意が必要です。
また、薬物療法は、尿酸値のコントロールに大変有効です。最近では1日1回のお薬もあります。自覚症状がなくても治療を継続することが重要です。