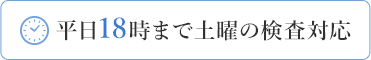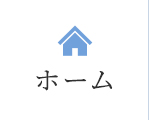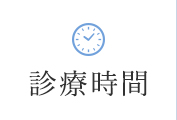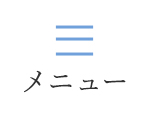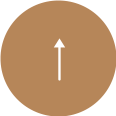便秘

便秘は「体外に排泄すべき便が、適切な量かつスムーズに排便できない状態」と定義されています(慢性便秘症診療ガイドライン)。毎日排便していても量が少ない、残便感がある、薬の服用や強くいきまないと排便できないなど、スムーズに排便できない状態が便秘です。
便秘には個人差があり、原因も多岐にわたります。当院では、適切な検査を行って原因を調べ、原因とご本人の状態やライフスタイルに合わせた治療を行っていきます。市販薬もたくさん売られていますが、便秘の治療薬は薬ごとに作用機序が異なり、新しい作用の薬や漢方薬も処方できるようになっていますので、市販薬でよくならない場合も改善が期待できます。便秘が続くことで発症しやすくなる疾患もあるので、便秘でお困りのことがありましたら、ご相談ください。
このような症状はありませんか?
- 便が3日以上でない
- コロコロした便が出る
- 強くいきんでも少ししか排便できない
- 数日間排便できていない
- お腹がひどく張り、苦痛がある
- 残便感がある
- 下痢と便秘が交互に訪れる
- 排便で改善する腹痛がある
- 血便やタール便(黒い便)が出る
- 便秘薬を使用しないと排便できない など
便秘の原因
便秘には生活習慣が大きく関与しています。
ストレス
便秘の原因の多くはストレスによるものと言われています。消化した食べ物を腸の中で動かしたり排出したりする腸管の蠕動運動は、交感神経と副交感神経のバランスによって保たれています。ストレスがかかると交感神経が優位になり、動きが停滞して便秘になります。
完璧主義や、せっかちな性格によってストレスが溜まることも多くあります。
引用:わかもと製薬
肉中心の食生活、食物繊維不足
肉類に含まれる動物性タンパク質は、過剰にとり過ぎると悪玉菌のエサになって腸内細菌を悪化させることがあります。また野菜には消化吸収されずに大腸まで届く水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が含まれており、便秘解消につながります。
- 水溶性食物繊維:水に溶けてゲル状になり、便を柔らかくして排便を促します。
- 不溶性食物繊維:水に溶けにくく、水分を吸収して膨らむことで腸の蠕動運動を促したり、便のカサを増やしたりして、排便を促す効果を期待できます。
水分の摂取不足
便は水分を含んでいるからこそ、容積が膨らみ、移動しやすい硬さとなります。
水分の摂取が足りないと、便の水分量もへり、カチカチの硬い便となるため排出しにくくなります。
過度のダイエット
腸内にはある程度の便がないと、排便が難しくなります。また、ダイエットでは脂質を制限することがありますが、脂質は便の滑りを良くする作用があります。さらに、脂質に含まれる脂肪酸は大腸を刺激して蠕動運動を促進する効果が期待できるため、適度な脂質の摂取が便秘解消に役立ちます。
おなかの冷え
お腹が冷えると交感神経が優位になり、腸の血行不良や蠕動運動の低下を招きます。これにより、腸内に便がとどまりやすくなるため、便秘につながります。
また、慢性の便秘には大腸の機能が悪くなることで起こる「機能性便秘」と、腸の物理的変化が原因の「器質性便秘」があります。
「機能性便秘」 以下の3つのタイプに大別されます。
弛緩性便秘
腸管の緊張が緩んで生じる便秘です。腸管内に長時間便が留まるため、便から水分が過剰に吸収されてしまい、硬くなって排便が困難になります。腹部膨満感や残便感、食欲低下、肩こりや肌荒れなどといった症状を伴うことがあります。女性や高齢者に多く、日常生活では運動不足や筋力の低下、水分・食物繊維の不足や過度なダイエットなどが誘因となります。
痙攣性便秘
環境の変化などのストレスや、過敏性腸症候群などが原因となり、大腸が過剰に緊張して、便をうまく先に送れなくなっている状態です。便秘と下痢を繰り返したり、便がコロコロした状態となり、食後の腹痛や残便感を生じることがあります。
直腸性便秘
高齢者に多い便秘で、便が肛門近くまできているにもかかわらず、排便反射が起こらず排便できない状態です。便意の我慢によって生じることが多く、痔が痛くて排便を我慢したりしていると、直腸性便秘を起こすことがあります。
「器質性便秘」
腸に狭いところや器質的に硬くなっているところがあって便秘になります。腸の癒着やねじれ、大腸がんなどの可能性があります。この状態の時に下剤を使用すると、腸穿孔を起こす可能性があるので、早めの受診が必要です。
生活習慣によって便秘が起きている場合、生活習慣の見直しが有効です。なお、内科疾患や消化器疾患によって便秘が起きている場合は、原因疾患の早期発見・早期治療が欠かせません。
便秘の検査
問診で便秘の状態や症状などをお聞きします。特に、市販薬や、漢方、ダイエット目的のサプリメントなどを服用している場合は治療のために大切な情報ですのでお伝えください。
問診と触診後、腹部超音波検査、腹部CT検査、大腸カメラ検査などを実施します。便秘が続く場合は、大腸がんなどの多くの大腸疾患の確定診断が可能な大腸カメラ検査を受け、原因をしっかり確認することが重要です。
便秘の治療
検査で原因疾患が判明した場合、その治療を行います。それ以外の原因で便秘が生じている場合は、食事や生活習慣、排便の方法などの改善し、薬物療法を併用して便秘の改善を図ります。生活習慣の改善では以下を意識しましょう。
食事
1日3食の食事を規則正しい時間に食べる。
排便を促すきっかけとなる朝ごはんは毎日食べる。朝起きたらコップ1杯の水を飲むことも大切です。
水分を十分にとる。
「1日の水分の摂取量目安は2.5リットル(内訳:食事から1リットル、飲料水から1.2リットル、体内で作られる水0.3リットル)とされており、1日かけてこまめに水分を補給するようにしましょう。」
食物繊維を十分にとる。
不溶性食物繊維を多く含む野菜は、便のボリュームを増やしてくれる一方、海藻やきのこ、納豆などに多く含まれる水溶性食物繊維は便をやわらかくしてくれます。ご自身に適した取り方を心がけることが大切です。
【食物繊維が多い食べ物】
- 穀物:玄米ごはん・ライ麦パン・オートミールなど
- 海藻類:わかめ・ひじき・めかぶなど
- 芋類:さつまいも・こんにゃく・山芋など
- きのこ類:きくらげ・干ししいたけ・なめこなど
- ドライフルーツ:柿・ブルーベリー・なつめ・いちじくなど
- 豆類:納豆・あずき・いんげん豆など
ダイエットなどの過度な脂肪制限は避ける
腸内環境を整える食品を積極的にとる。
乳酸菌は腸内で乳酸を産生することにより悪玉菌の発生を抑制し、善玉菌の増殖を促します。善玉菌が増えると便の量が増加しスムーズな排便につながります。乳酸菌を含むヨーグルトやチーズ、納豆などの発酵食品、玄米や大豆などに含まれるオリゴ糖などは、腸内環境を整え、便秘を解消する効果が期待できます。
排便習慣の改善
便意があったら我慢せずにトイレに行くことや、トイレに長い時間座らないといった排便習慣の改善も大切です。また、排便時の姿勢は、便の通り道がまっすぐになる前傾姿勢を試してみるのも良いでしょう。
適度な運動を習慣にする
また、生活習慣の見直しと同時に薬物療法を実施することも大切です。
便秘薬には様々なラインナップがあります。市販薬(サプリメントや漢方を含む)は症状悪化や副作用のリスクを持つものが多数あるため、ご自身の判断で使うことはお勧めしません。当院では、患者様の状態に細かく合わせたお薬を使用していますので、便秘治療について不明点や不安なことなどがあれば、お気軽にご相談ください。
下痢

便の水分量が多くなり、形状を保つことができず液状または泥状のまま繰り返し排出される状態です。
一般的に便の水分量は70~80%ですが、軟便が80~90%、90%以上が水様便とされています。
下痢の原因
過度な飲酒、暴飲暴食、刺激物や香辛料の摂取など日常的な原因によって起こることも多いですが、細菌やウイルスによる感染症、過剰なストレス、様々な大腸疾患でも下痢を起こすことかあります。
日常的な原因で起こる下痢
- 暴飲暴食
- 過度のアルコール摂取
- 乳製品をたくさん摂取したとき
牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素が少ない人(乳糖不耐症の人)が、牛乳をたくさん飲むと乳糖の分解が間に合わず腸内に蓄積します。乳糖が水分を引き寄せてしまうため下痢になります。 - 内服薬
感染性腸炎(細菌やウイルスによる感染症)
細菌が原因
| 病原微生物 | 主な感染源 | 潜伏期 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌 | おにぎり | 食後1-6時間 | 下痢、腹痛、嘔吐 加熱しても食中毒の原因となる毒素は分解されない |
| カンピロバクター | 鶏肉 | ||
| サルモネラ | 卵や食肉を生で食べる | 食後12-48時間 | 発熱、下痢、腹痛、嘔吐 |
| 腸炎ビブリオ | 魚介類 | 食後4-96時間 | 激しい下痢、腹痛、血便 |
毒素が原因
| 病原微生物 | 主な感染源 | 潜伏期 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| 腸管出血性大腸菌(O-157) | 火が通っていない肉や野菜 | 食後12-60時間 | 激しい下痢、腹痛、下血 |
| ボツリヌス菌 | 長期保存する食品 | 食後8-36時間 | 下痢、嘔吐、麻痺 |
| コレラ菌 | 生の食材 | 食後2-3日 | 激しい下痢と嘔吐 脱水 |
ウイルスが原因
| 病原微生物 | 主な感染源 | 潜伏期 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 二枚貝の生で食べる | 食後1-2日 | 激しい下痢、嘔吐、腹痛 |
| ロタウイルス | 乳幼児、接触感染 | 2-4日潜伏期 | 下痢(激しい時は白色) |
急性の下痢と3~4週間持続している慢性の下痢に分けられます。
急性下痢
分泌性下痢
食中毒や急性胃腸炎の時に見られる下痢です。腸の粘膜がダメージを受けることにより、腸管内の分泌液が過剰になり下痢になります。
浸透圧性下痢
食べ過ぎにより腸にかかる負担が増加したり、腸の消化・吸収能力が低下したりすることにより起こる下痢です。過度のアルコール摂取や、脂質の多い食事習慣、甘味料(ソルビトール、キシリトールなど)の摂取など、水分を引き込もうとする成分が腸内にあると、下痢を起こします。
慢性下痢
運動亢進性下痢
ストレスや冷えなどで、自律神経のバランスが崩れ腸の運動が過敏になることにより、水分が腸管で吸収されず下痢になります。
滲出性下痢
腸管に炎症が起こることで、腸管の組織液(滲出液)が腸管内にもれることにより下痢をきたします。潰瘍性大腸炎やクローン病といった腸管内に慢性的に炎症を起こす疾患が原因となります。
受診の目安
早急な対応を必要とする下痢
- 1時間に1回以上、下痢便が出る
- 38℃以上の発熱や激しい腹痛が起こっている
- 下痢の他に大量の鮮血便が出た
- 下痢だけでなく嘔吐が起こり、しっかりと水分補給ができない
下痢を起こす消化器疾患
- 感染性腸炎
- 過敏性腸症候群
- 潰瘍性大腸炎・クローン病
- 大腸がん
下痢の検査と治療
原因を特定するために、問診で下痢が起こり始めた時期、便の状態、回数、生活習慣などを確認します。その後、腹部の触診や聴診を行い必要に応じて、血液検査、便の培養検査、大腸カメラ検査などを実施します。
急性下痢の場合
暴飲暴食や食あたり、ウイルス性胃腸炎などによる急性下痢の場合は、ほとんどが自然治癒を期待できます。その間、水分摂取を十分に行い脱水の補正をすることが大切です。
慢性下痢の場合
血液検査や大腸カメラ検査を実施します。大腸がんや炎症性腸疾患などの発症者数は昨今増え続けており、早期発見・早期治療が欠かせません。下痢が続く場合は早めにご相談ください。